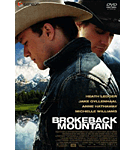 私は、今まで自分が生きてきた時間の影響もあって、想像力は強い方だと思う。だから、『ブロークバック・マウンテン』で、ホモフォビアによって惨殺された死体の映像が出てくると、どう抑えようとしても「もし自分があんな目に合うことになったら……」とイメージがふくらみ、気分がはなはだしくロウになる。
私は、今まで自分が生きてきた時間の影響もあって、想像力は強い方だと思う。だから、『ブロークバック・マウンテン』で、ホモフォビアによって惨殺された死体の映像が出てくると、どう抑えようとしても「もし自分があんな目に合うことになったら……」とイメージがふくらみ、気分がはなはだしくロウになる。
さらに、ストーリー的にも主人公のひとりジャック・ツイストがホモフォビア[同性愛嫌悪/同性愛恐怖症=同性愛が差別されるのは社会の寛容さのなさに問題があることを表した言葉]で殺されたことが示唆されるともうダメである。映画そのものに加えてそのことだけでも、哀しくなってしまう。どうしたらこんなことが起きなくなるのか、考え込んでしまう。
率直に言えば、それと同時に私とパートナーが20年間とにもかくにも寄り添い続けてこれたことに、ホッとしてしまう感情も起こったことを言わざるを得ない。
■
■ ■ ■ ■ ■
というわけで、やっと時間を作って、パートナーといっしょに映画『ブロークバック・マウンテン』を観てきた。
監督のアン・リー(監督賞/台湾出身)を始めとして、今年のアカデミー賞で3部門を受賞した作品。アメリカ西部はワイオミング州にあるブロークバック・マウンテンで羊の放牧の季節労働をふたりでやることになって知り合ったイニス・デルマーとジャック・ツイストが愛をはぐくんでいく物語だ。
キャッチフレーズに「映画史上、最も心揺さぶられる愛の物語」とある通り、人を心から愛することの意味、とりわけ愛の大きさと大切さは失ってからいっそうわかるものだという悲しい真実、愛はしばしば妨げられ虐げられそれに耐えられないこともあるという切ない事実……が実に巧みな映像とともにいやというほど伝わってくる。
しかし、この映画はそこだけ見ていたのでは、爆発的かつ斬新な感動を得た感じにはならない。そんなにすごい映画なんだろうか、とさえ思ってしまう。LGBT
を題材にしたものとしても、同レベルの映画はいくつもあげることが出きる。
ポイントは、私が想像力からおびえたところにある。この映画にはホモフォビアそのものがきっちりと、しかし押しつけがましくなく描かれているからすごいのだ。
■
■ ■ ■ ■ ■
まず、イニスが自分の中の同性指向をなかなか受け入れようとしない背景にそれが現れる。
ジャックはイニスに、ふたりで暮らそうと迫る。ふたりで牧場を経営して生きていこう、と強く強く訴える。しかしイニスは、今の生活を変えることはできないと、かたくなに拒否する(イニスは正確にはゲイというよりバイセクシュアルかも知れない)。
その理由は、女性と結婚してしまい子どももいるから、などといった単純なものだけではないことが映画の中にさりげなくちりばめられている。
例えば、イニスは9歳の時に、父親に男性のむごい惨殺死体を見せられる。当時ワイオミングで男ふたりで愛し合って暮らしていたゲイが、男同士だという理由だけで住民に虐殺されたのだ。その父親もその虐殺に手を貸しており、幼いイニスの脳裏には、同性を愛すること=死、というイメージが強烈に焼き付けられる。
イニスの頭には絶えずこの9歳の時の体験がフラッシュバックして、ジャックへの愛にブレーキをかける。妻と離婚してからでさえ、ブレーキをかけまくる。ジャックを愛していながら、いや愛せば愛すほど、そこから逃げたくなるほど恐怖心も比例して増えてくる。ジャックとともに生きていくイメージをどうしても作れない。
■
■ ■ ■ ■ ■
そんな中で、ジャックの事故死が知らされるが、ゲイだとわかってリンチを受けて殺されたのではないか、と暗示するカットや演技がたくさんある。イニスもそれを感づいたはずだ。
そしてラストシーンで、イニスは一生ジャックの思い出といっしょに生きていこう、と決意する。それはふたりが会ってふたりだけの時間を過ごせた唯一の場所、ブロークバック・マウンテンの思い出に等しい。ジャックは、死なないと、イニスからの愛を受け取れなかったのである。切ない、あまりにも切ない。そしてこれはホモフォビアがその源にある。
■
■ ■ ■ ■ ■
ホモフォビアは映画全体にちりばめられている。ジャックがイニスと出会った翌年、再び季節労働を求めて牧場に行くと、前年のイニスとの関係がばれていて、職を得られない。
さらにふたりとも、自分の同性指向が自分の住む地域に知られた時の怖さを自覚しており、人の視線やおしゃべりに過剰反応してしまうことも示唆される。
ちなみに、ホモフォビアによる虐殺は今の米国でも現実に起こっていることで、絵空事ではない。1998年10月、奇しくもこの映画の舞台と同じワイオミング州はララミー市の近郊で、同市の大学に通うマシュー・シェパードさんがゲイであるという理由で暴行を受け、さらにフェンスにくくりつけられて、意識がなくなるまで銃でたたかれ、置き去りにされ亡くなる、という事件があった。
■
■ ■ ■ ■ ■
問題は、映画にちりばめられたホモフォビアを観客が意識できるかどうか、である。すでに公開されて1ヶ月以上経つので、たくさんのレビューや感想をネットで読むことができるけれど、ホモフォビアに言及されているものはそう多くない。
これはむっちゃくっちゃ残念なことではあるのだけれど、わかる人にだけ伝わればいいのかもしれない、と思うしかない。ホモフォビアが見えない人は「不倫」の映画だなどと書いてもいる。登場人物のすべてが「不幸」になってしまう社会構造が見えないとこの映画の意義はわからなくなる。
ホモフォビアを「隠しテーマ」とすることは、アン・リー監督も間違いなく意識している。しかしインタビュー等では、めいっぱい「普遍的な愛の物語」であることを強調している。
このことにこそ現代にもまだホモフォビアが存在することが示されている。本当は「メインテーマ」かもしれない「隠しテーマ」をおおっぴらに言ってしまうわけにはいかないのだ。だから、当事者団体のGLAAD(中傷と闘うゲイ・レズビアン同盟)から第17回GLAADメディア賞(作品賞)を受賞した時、監督はかなりよろこんで「やっと実際に大きな意味を持つ賞をいただけた」とコメントしたそうだから。
実際、米国内でも上映を拒否する映画館チェーンが現れたし、この映画へのバッシングもたくさんある。バハマや中国では上映禁止になっている。
■
■ ■ ■ ■ ■
そして私はさらに、深読みをする。パートナーが、この映画には「善人」がほとんど出てこない、と言うのだ。そう言われてみると、登場人物たちが誰ひとりとして「生き生きと」暮らしていない。自分らしさを発揮できないか、忘れてさえいて、世間を始めとするいろいろなものに縛られ息苦しいのに、妙に強気で生き急いでいる姿が思いっきり伝わってくる。
それは当時の、そして現在の米国を象徴している。超大国に、多様な生き方や多彩な人間を受け入れる「包容力」あるいは「優しさ」がないことを表している。何しろイニスもジャックも、誰にも自分の苦悩を相談できないどころか、気持ちを楽にしてくれる友だちもいないのだ。
同性愛者を受け入れられない社会は、少しでもレールからはみ出したりすればものすごいプレッシャーがかかる社会とイコールだ。結局誰にも「優しく」ない。アン・リー監督が台湾出身であるがゆえに、ひそかにそれを問うまでの想いを込めたのではないか、どうしてもそう深読みしたくなる作品だ。
■
■ ■ ■ ■ ■
だとするとこの映画は、宣伝用「表テーマ」(愛)と「裏テーマ」(ホモフォビア)とさらに「超隠しテーマ」(米国の影の部分)があるものすごい仕掛けになっていることになる。
そこにこそ感動する、ということは「映画史上、最も心揺さぶられる愛の物語」とはみなさないことでもある。この映画のあり方そのもの、制作されて上映されて賞をもらうプロセスそのものが、現代社会の構造を掘り起こしているのだ。
だから、愛だけではなく自分や家族や社会・国家を考え直させられる作品として、ぜひ一度観てほしい。あなたが変わるかもしれないから。